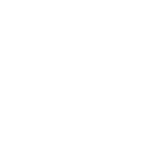日本では医療機関で確認された妊娠の約15%が流産となり、横浜市における死産数は令和3年度478件に上りました。この人数には12週未満の赤ちゃんは含まれないため、実際には更に多くの赤ちゃんが亡くなっています。
厚生労働省は『「妊産婦」とは妊娠中または出産後1年以内の女子をいい、この「出産」には流産及び死産の場合も含まれる』と法における位置付けを明記し、産後ケア事業等の支援には、流産や死産を経験した女性を含め、きめ細かな支援を行うための体制整備に努めるようにと通知を出していますが、小さな命の存在を知る人が少ないことや社会的になかなか理解が進まない等様々な理由により、これまで十分な支援は行われてきませんでした。
9月12日、横浜市会の令和5年度第3回市会定例会・一般質問に初登壇した際、市長に対し
「横浜市の流産や死産等で子供を亡くした家族への支援は十分とは言えず、心身ともに寄り添った支援とつらい思いを抱えた方が孤立せず助けを求められるよう、適切な情報提供を行うべきである」と要望したところ、
市長からは「必要な支援につながるよう、情報を集約したページを作る」と答弁をいただきました。
そして、この質疑がきっかけとなり、横浜市のHPには「流産や死産を経験された方へ」というページが公開され、各区の相談窓口や民間団体の情報が初めて掲載されました。
⚫︎流産や死産を経験された方へ
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/oyakokenko/shido/sodan/ryuuzan_sizan.htm
更に、このページの公開をきっかけに、横浜市助産師会のご理解・ご協力により、訪問型産後ケアについても掲載させていただくことができたと、担当課の方よりお知らせをいただきました。

流産や死産であっても陣痛は起き、産声のない出産をし、母乳が出るお母さんたちがいます。だからこそ、産後ケアは必要なのですが、小さな命を失った悲しみを抱えた方にとっては、元気な赤ちゃんの声が聞こえる病院でケアを受けることは非常に辛いことです。今回こうして助産師会のご協力によって訪問型のケアを受けられる窓口ができたことは大変意義のあることだと感じています。
⚫︎【死産・流産された方】横浜市産後母子ケア事業(訪問型母子ケア)利用申請
私自身、2年前に妊娠・出産をしたことにより、誰にでも流産や死産をする可能性があることを実感した一方、あまりにも知識を備える機会や支援体制がないことを認識しました。そのような中で、「横浜市で流産を経験したけれど支援がなく、辛かった」という市民の方のお声を実際にお聞きし、質疑をすることにいたしました。今回、当事者の方のお声が届いたことにとても感激しています。
心や身体が辛いと感じられた時、どうかお一人で抱えず、行政へのご相談やこうした支援をご自身のタイミングでご活用してください。
お声を寄せてくださった方、そしてご尽力くださった横浜市ご担当のみなさまに心から感謝申し上げます。 私自身一人の母親として、どんな方にもあたたかく寄り添える横浜市であり続けられることを目指し、これからも取り組んでまいります。