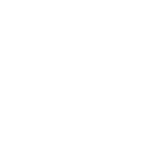昨日は、横浜市会の本会議にて、都筑区民の方々からの声を背負い、一般質問を行いました。4月に当選してから初めての登壇となりました。
本会議の録画配信はこちらから見ていただけます。
今回の質問は、すべて皆さんからいただいたご意見をもとに練り上げました。前向きな回答が得られなかったものも残念ながらありますが、いただいた任期のの四年をかけて、引き続き粘り強く取り組んでいきたいと考えています。 12分という限られた時間の中で質問した大きなテーマは、以下の4つです。
- 放課後キッズクラブ事業の充実
- 小・中学校の校務支援システムの課題への対応
- 子どもの弱視等眼疾患の早期発見に向けた取組
- 流産や死産を経験した方や御家族へのケア
それぞれのテーマごとに、質問と回答をまとめたいと思います。

【放課後キッズクラブ事業の充実】
①長期休業期間に昼食を提供すべき
→様々なご意見をもらっている。事業者、保護者等にアンケート調査を実施し、その結果を踏まえ引き続き検討する
②夏休み期間中の安全で快適な活動場所の確保
→特別教室などを一時的に利用し、引き続き安全な居場所確保を行う
③放課後キッズクラブの「子どもの育ちの場」としての充実に向けた取組
→今後もご意見を伺いながら事業の充実に取り組む
【小・中学校の校務支援システムの課題への対応】
①校務支援システムの課題をどうとらえているのか
→国の専門家会議で挙げられた課題の多くは本市の課題でもある。特に働き方に選択肢が少ないことやデータ連携が困難なことは、サーバー設置の災害対策が不十分であることは、大きな課題
②校務支援システムの課題解決に向けた今年度の取組
→多くの学校では個別にソフトウェアを入れているので、ファイルサーバの使われた方の現状を確認する調査を行う
③校務支援システムの今後に向けた考え
→職員室に限定されない柔軟な働き方、校務形と学習形・小学校と中学校のデータ連携、システムのクラウド化やセキュリティの確保を実現していく。安全性を考慮し、学校と対話しながら進めていく
【子どもの弱視等眼疾患の早期発見に向けた取組】
①3歳児健診において、屈折検査機器による検査を実施すべき
→視覚検査は日本眼科医会のマニュアルで3歳半で行うことが望ましいと言われている。3歳児健診を3歳6ヶ月で行うと他の障害の発見が遅れるリスクがある。屈折検査機器を用いるには集団で行う必要があり、健診と別に行うと保護者の負担が増加する
②弱視に対する周知・啓発の取り組みを強化すべき
→今後もより手法について検討し、認識してもらえるよう取り組む
【流産・死産を経験した方やご家族へのケア】
①流産・死産を経験した方への寄り添った支援についての見解
→現在も支援の希望があった場合、個別に話を伺っている
②流産・死産を経験した方への支援などの情報提供について
→必要な支援につながるように、本市のウェブサイトに区の相談窓口や民間団体の支援に関する情報を集約したページを作る
原稿の全文
民主フォーラム横浜市会議員団の深作ゆいです。会派を代表して順次質問してまいります。
まず、放課後キッズクラブ事業の充実について伺います。
本市の学校施設を活用した放課後の居場所として、放課後キッズクラブ事業があります。平日の放課後はもちろんのこと、特に夏休みなどの長期休業期間中には、お子さんが朝から夕方までの長時間を過ごす場所として、重要な役割を担っています。 私の地元である都筑区でも、実際に利用されている保護者の方々から、キッズクラブでの夏休みの過ごし方について、暑さ対策や昼食の提供など、様々な要望をお聞きします。現在、キッズクラブでは昼食の提供は行われておらず、夏休みや冬休みなどの長期休業期間中は、多くの保護者がお弁当を用意し、子どもたちが持参しています。毎日続くお弁当作りは、特にきょうだいが保育園に通っていて送迎が必要な方や、ひとり親の方々にとって大きな負担となっています。
一方、令和5年4月に行われた市職員を対象にした「放課後事業に関するアンケート調査」でも、66.4%の職員が「長期休業日等の昼食提供」を求めており、様々なご家庭の状況や多忙を極める方への選択肢の一つとして、キッズクラブにおける昼食の提供は、喫緊の課題であると考えます。そこで、
(1)長期休業期間に昼食を提供すべきと考えますが、市長の見解を伺います。
同じく夏休みの過ごし方については、活動場所の確保も重要です。今年は、例年にない猛暑が続き、外遊びが困難な日も多かったことから、学校施設を活用したキッズクラブでは、十分な場所が確保できず、限られたスペースの中で多くの児童が過ごしていたようです。そこで、
(2)夏休み期間中の安全で快適な活動場所の確保について市長に伺います。
放課後キッズクラブは、放課後の長時間を過ごす場所であるため、児童を安全に見守るだけでなく、お子さんが様々な遊びや体験活動などを通じて成長していく場として、多くの保護者から期待されていると認識しています。 一方で、一部の保護者からは、子どもたちの成長につながるような活動が少ない、という意見も聞いております。そこで、
(3)放課後キッズクラブの「子どもの育ちの場」としての充実に向けた取組について市長に伺います。
子どもたちや現場の声を聞きながら、よりよい放課後の居場所づくりを進めていただくことを期待して、次の質問に移ります。
本市では、教員の受験者数が小中学校ともに年々減少傾向にあり、先生の働く現場の環境改善は喫緊の課題です。令和4年度「教員勤務実態調査」の速報値でも、教員の週あたりの在校時間は小中学校ともに50時間以上となっており、看過できない勤務実態が示されています。先生が心身の健康を損なうことなく児童生徒たちと向き合う時間を確保していくための具体的な解決策の一つとして、 児童生徒の出欠席や成績情報、保健データ等を管理する「統合型校務支援システム」の導入により、業務の効率化などを図ることが必要であると感じます。
本市でも、校務支援システムは導入されていますが、その他の業務システムとの連動性は少ないことに加え、小学校と中学校で利用している校務支援システムがそれぞれ別のシステムであるため、教職員にとって一定の負担となっていると伺いました。そこで、
(1)校務支援システムの課題をどうとらえているのか、教育長に伺います。
学校では、個々の児童生徒に紐づかないデータ、例えば、学年指導計画などは、学校内に設置されているファイルサーバに保存しているそうですが、オンプレミス、つまり自前での設置では、災害時等に業務の継続性が損なわれる危険性が高いと考えています。
本市の校務用ファイルサーバのリース契約が、早いもので令和7年度に切れることを踏まえると、例えば、セキュリティ対策を講じた上でサーバのクラウド移行等を検討するなど、全体要件を整理し、方向性を決めていく必要があると思います。そこで、
(2)校務支援システムの課題解決に向けた今年度の取組について、教育長に伺います。
GIGAスクール構想により、市立学校の児童生徒に1人1台の端末が配布され、各学校に高速大容量の通信ネットワークが整備されました。これと比較すると、校務のデジタル化の状況はまだまだ遅れていると考えます。そこで、
(3)校務支援システムの今後に向けた考えについて、教育長に伺います。
今後は、教職員の利便性・セキュリティ構成などを考慮した、将来を見据えた校務処理システムの構築を図るとともに、新たなシステムの導入に際しては、他自治体への導入実績や現場の教職員の声を十分反映すること、また、ヘルプデスクなどをおき、サポート体制の充実にも取り組むことをお願いして、次の質問に移ります。
次に、子どもの弱視等眼の疾患の早期発見に向けた取組について伺います。
こどもの視力は、3歳頃までに急速に発達し、6歳から8歳頃に成人とほぼ同等になり、生涯の視力が決まります。そのため、3歳児に実施する視覚検査は、視力の発達の遅れや弱視、眼の疾患を早期に発見し、治療へつなげる重要な機会となります。
本市では、一次検査は保育士、保護者等によって行われ、そこで異常があると判断された場合、視能訓練士による二次検査が実施されます。しかし、3歳の子どもの子育てをするお母さん達に話を聞いても、視力検査を親が正確に行い、視力の異常まで気づくことは難しいと言わざるを得ません。また、3歳児では見えにくさを感じていても「見えにくい」と言葉で伝えることが難しいため、現在の本市の3歳児健診の方法では、弱視が見逃されている可能性があると考えます。
最近では、子どもの応答に左右されず、客観的に弱視のリスクを推測できる屈折検査機器が開発され、国においても、屈折検査機器等の整備を行う際に活用できる補助事業が創設され、導入が促されているところです。
私は、本市でも3歳児健診において、全ての子どもに屈折検査を実施することが、弱視の見落としを減らすことにつながると考えます。そこで、
(1)3歳児健診において、屈折検査機器による検査を実施すべきと考えますが、市長の見解を伺います。
弱視の発見率を向上させるには、周囲の大人がこどもの目の状態について早期に気づいてあげることも必要です。保護者に視覚検査の重要性について認識してもらうために、両親教室や乳幼児健診の機会で周知するなど、より工夫ができるのではないのでしょうか。そこで、
(2)弱視に対する周知・啓発の取り組みを強化すべきと考えますが、市長の見解を伺います。
横浜市のすべての子どもたちに視覚障害を克服するチャンスを提供し、成長と発達の保証をするためにも積極的に取り組んでいただくことを期待して、次の質問に移ります。
最後に、流産・死産を経験した方やご家族へのケアについて伺います。
日本では、医療機関で確認された妊娠の約15%が流産となり、本市における死産数は令和3年度478件にのぼります。この人数には12週未満の赤ちゃんは含まれないため、実際にはもっと多くの赤ちゃんが亡くなっています。その小さな命の存在を知る人が少ないこともあり、社会に認められにくい悲嘆とも言われ、どこからも支援を受けられず孤立してしまったり、喪失感や辛い気持ちを語れる場所がないまま社会復帰をせざるを得ない状況になるなど、これまで十分な支援が行われてきませんでした。
この状況を受け、厚生労働省は令和3年5月、「妊産婦」とは妊娠中または出産後1年以内の女子をいい、この「出産」には流産及び死産の場合も含まれると法における位置付けを明記し、産後ケア事業や、子育て世代包括支援センターにおける支援には、流産や死産を経験した女性を含め、きめ細かな支援を行うための体制整備に努めるようにと通知をしています。
一方、本市では、残念ながら流産や死産を経験した方が受けられる支援に関する情報はホームページ等に見当たらず、唯一、各区の戸籍課にて死産の手続きをされた方に、電話等で相談対応が可能な旨を書いた紙を用意しているのみでした。しかしそれも、必ずしもお渡しされているわけではないようです。辛い思いを抱えた方が孤立せず、周囲に助けを求められるよう、本市でも、流産や死産を経験した女性やその家族に対し、心身ともに寄り添った支援を行うべきと考えます。そこで、
(1)流産・死産を経験した方への寄り添った支援について、市長の見解を伺います。
厚生労働省が行った流産・死産を経験した女性の相談ニーズ調査においては、専門的な相談をしたいと答えている人が35%いるにも関わらず、地域の相談窓口や保健センターに相談した人はわずか5.2%しかいないことや、支援を必要と感じた女性の多くがうつや不安障害が疑われる状況にあったことが明らかになっています。
本市として、産後ケア事業をはじめ、同じ経験をした人によるピアサポートグループなどの情報を、適切に周知することが必要であると考えます。そこで、
(2)流産・死産を経験した方への支援などの情報提供について、市長に伺います。
流産や死産であっても陣痛は起き、産声のない出産をし、母乳が出る。そんな経験をする母親とその家族がいます。その方々に温かく寄り添える横浜市であることを願って、わたくしの質問を終わります。ありがとうございました。